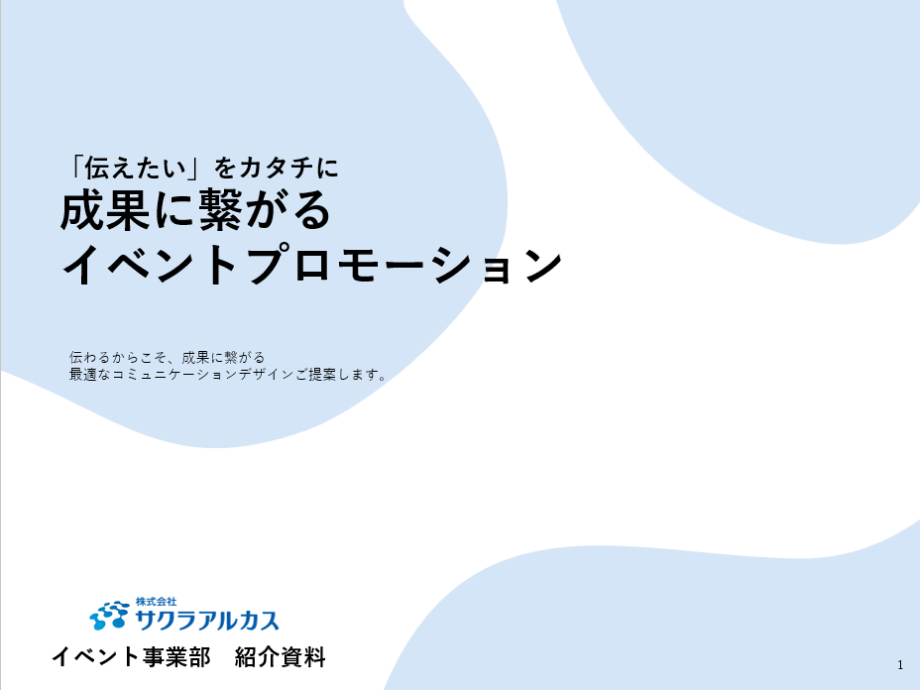これで焦らない! ~展示会の出展準備とスケジュールを徹底説明~

展示会出展は、自社の製品やサービスを多くの人に知ってもらう絶好の機会です。しかし、準備すべきことが多く、初めての方にとってはハードルが高く感じるかもしれません。
この記事では、展示会出展までの流れを8つのステップに分け、それぞれのステップで何をすべきか、焦らず準備を進めるためのポイントを解説します。
▼この記事はこんな人におすすめ
- 展示会の出展を検討しているご担当者様
- 展示会でいつまでに何を準備したらいいか分からないご担当者様
出展する展示会と目的・目標を決定(6~5か月前)

出展の目的
展示会への出展目的を明確にすることが成功への第一歩です。
例えば、以下のような目的が考えられます。
- 新規顧客の獲得
- 既存顧客との関係強化
- 新製品・サービスのPR
- 業界内でのブランディング
目標設定
展示会の成功を測るためには、明確な数値目標(KPI)を設定し、最終的なビジネス成果(KGI)と紐づけることが重要です。
▼KPI(短期的な指標)の具体例 展示会当日の活動を可視化し、成果を測るための指標です。
・名刺交換枚数:1,500枚(3日間で1日あたり500枚)
・商談件数:30件(1日10件の商談を実施)
・リード獲得数:200件(ターゲット顧客との深い接点)
・ブース来場者数:2,000人(呼び込み施策を活用)
・デモンストレーション参加者数:100人(製品の理解促進)
▼2. KGI(最終的な成果指標)の具体例
・展示会の本来の目的(売上や契約の獲得)に直結する指標です。
・獲得リードからの商談化率:30%(200件のリードのうち60件が商談に発展)
・商談からの受注率:20%(60件の商談から12件の成約)
・受注金額:2,400万円(1件あたり平均200万円の契約×12件)
・ROI(投資対効果):出展コスト500万円に対し、売上2,400万円でROI 4.8倍
展示会の選定と申し込み
展示会には規模が大きいものから小規模なものまでさまざまあります。自社のリソースや目標に合った規模の展示会を選ぶことが重要です。また、参加者の業種や背景が自社のターゲット層と一致しているかも確認しましょう。
▼以下のサイトより開催予定の展示会を確認できます。
日刊工業新聞電子版 イベントスケジュール全国主要見本市・展示会一覧 Web版
https://biz.nikkan.co.jp/brand/eventexpo
日本貿易振興機構(ジェトロ) 世界の見本市・展示会情報(J-messe)
https://www.jetro.go.jp/j-messe/country/asia/jp
展示ブースのテーマとコンセプトの決定(5か月前)
展示製品・サービスの選定
出展する製品・サービスを決定し、ターゲットに刺さる訴求ポイントを明確にします。単に製品を紹介するのではなく、「誰に」「どのような価値を」「どんなシーンで提供できるのか」 を具体的に整理することが重要です。
また、来場者の第一印象を左右するキャッチコピーを戦略的に設定しましょう。キャッチコピーは、ブースの印象を決め、興味を引きつける最初のフックとなります。
特に展示会では、来場者が短時間で多数のブースを巡回するため、3秒で伝わるコピーを意識しましょう。キャッチコピーが適切であれば、興味を持った来場者が足を止め、次の会話につながる可能性が高まります。
概算予算の作成
展示ブースの設営、装飾、運営にかかる費用を事前に見積もり、全体の予算を策定します。主な費用項目としては以下のようなものが挙げられます。
・ブーススペース費用(出展エリアのレンタル費)
・ブース設営・デザイン費(什器、装飾、ディスプレイ制作費)
・販促ツール費用(パンフレット、ノベルティ、サンプル品)
・人件費(スタッフの派遣・研修・宿泊・交通費)
・プロモーション費用(事前告知、Web広告、SNS施策)
また、ブースの規模や展示方法によって費用感が大きく異なるため、目的に応じた費用対効果を考慮しながら予算配分を最適化することが重要です。
展示ブース施工の協力会社選定(4か月前)
展示ブースのクオリティや完成度を左右する重要な要素の一つが、信頼できる施工の協力会社を選定することです。ブースの設営はデザインの見栄えだけでなく、機能性や安全性、当日の運営のしやすさにも大きく影響します。そのため、単にコスト面だけで判断するのではなく、実績・提案力・対応力を総合的に考慮した選定が求められます。
施工会社を選ぶ際には、過去の施工実績を確認することが重要です。特に、自社の業界や製品特性に合ったブースの制作経験がある会社であれば、ターゲットに響くデザインやレイアウトのノウハウを持っている可能性が高く、スムーズなやり取りが期待できます。また、実際の施工事例やクライアントの評判を参考にすることで、その会社の強みや得意分野を見極めることができます。
ブースのレイアウトやデザイン、コンセプト、予算を明確に伝え、具体的な提案を受けることが大切です。施工会社によっては、予算内で最大限の効果を発揮できるようなアイデアを出してくれることもあり、コストパフォーマンスの高い設計が可能になります。
例えば、「限られたスペースでも視認性を高めるレイアウト」や「簡単に組み立て・撤収できるブース設計」など、運営のしやすさも考慮した提案を求めると良いでしょう。
ブースデザインと運営体制の決定(4か月前~2か月前)
施工会社との打ち合わせ
施工会社と細かい仕様やスケジュールを詰めていきます。
人員手配
当日の運営に必要なスタッフを確保し、役割分担を決めます。スタッフの役割には、受付対応、製品説明、デモ実演、商談対応などが含まれます。また、当日スムーズに運営できるように、事前にトレーニングやシミュレーションを実施しましょう。休憩時間も考慮しシフトを組むことで最適な人員計画で運営できるようになります。
制作物の準備
パンフレット、ポスター、パネルなどの制作を準備します。 デモ動画やプレゼン資料も必要に応じて準備します。 製品カタログやチラシを作成し、来場者が持ち帰りやすいものも用意すると良いでしょう。
来場者配布用ノベルティの準備
企業ロゴ入りのノベルティを用意し、来場者への印象を強めます。ノベルティ選びでは、実用性があり、来場者にとって価値のあるアイテムを選ぶことが重要です。例えば、エコバッグ、USBメモリ、ボールペン、メモ帳などが人気です。
アンケート用紙の準備

リード獲得のためのアンケートを作成し、来場者の興味関心や今後のフォローアップのための情報を収集できるようにします。紙媒体だけでなく、QRコードを活用したオンラインアンケートも検討すると、データ集計が容易になります。
展示物の準備と機材の手配、展示会出展の告知(1か月前)
必要な機材の手配
展示に必要な機材をリストアップし、確実に手配します。
- モニター、PC、タブレット
- 製品サンプルや実演用の機材
- 照明や音響設備
- 電源ケーブルや延長コード、配線整理用品
【ポイント】
大型モニターやスピーカー、マイクなどの特殊機材はレンタルの手配が必要になる場合があります。事前に機材の仕様を確認し、展示会場の設備と適合するかチェックしましょう。
搬入・搬出の準備
展示品の梱包方法を検討し、安全に運搬できるよう準備します。展示会場への搬入出スケジュールを確認し、必要な車両や運送業者を手配しましょう。
会場の搬入口や駐車場の使用ルールを事前に確認しておきましょう。
集客告知
企業のWebサイトやブログに展示会情報を掲載し、ニュース記事として発信することで、来場を検討しているターゲットに向けて早い段階から認知を広げましょう。また、X(旧:Twitter)やFacebook、InstagramといったSNSを活用し、展示会の見どころや出展製品の魅力を発信することで、興味を引き、参加意欲を高めることができます。
プレスリリースで、業界メディアや関係者に情報を届けることで、企業や製品の認知度を向上させ、展示会当日の集客をより効果的に促すことができます。
【ポイント】
予算に余裕のある企業は、展示会主催者が提供する広告枠やオンラインプロモーションを活用も検討してください。会場のリーフレットへの掲載や、会場の案内サインなどに掲載されるなど露出を増やすことができます。
ブースの設営(引き渡し)、リハーサル(会期前日:施工日)
ブース設営(引渡し)
基本的に、会期の一日前にブースが引き渡されます。
引き渡しとは・・・施工会社がブースの設営を完了し、出展者に最終確認を行ったうえで正式に使用可能な状態で納品することを「引き渡し」と言います。
ビジネスで言われる「納品」を意味しますので、引き渡し前に、しっかりと図面と相違がないかを確認してください。 その後、出展製品などの展示準備をしていきます。
機材のテスト・リハーサル
デモのリハーサルを実施し、プレゼンテーションの流れを確認します。PCや映像機器の動作確認を行い、不具合がないかチェックします。また、予備機材を用意し、トラブル発生時の対応策を事前に準備しておくことで、スムーズな運営を確保します。
展示会ブース運営、撤収(展示会 会期中)
運営の心構え
いよいよ展示会当日です。以下のポイントをおさえてブースの運営に努めましょう。
積極的な挨拶
来場者に対して、明るく元気に挨拶することで、ブースへの興味を引きます。スタッフ全員が積極的に声をかけ、親しみやすい雰囲気を作ることが重要です。
親しみやすい接客
来場者に対して営業トークばかりではなく、自然な会話を心がけることが大切です。来場者の関心に合わせた質問をし、相手の話をよく聞くことで、信頼感を築くことができます。また、専門用語を使いすぎず、分かりやすい説明を心がけましょう。
清潔で整理されたブースの維持
第一印象は非常に重要です。ブース内は常に整理整頓し、パンフレットやノベルティが乱雑にならないように管理しましょう。スタッフの服装や身だしなみもチェックし、清潔感のある印象を与えることが来場者の信頼につながります。
撤収作業
展示会終了後、撤収作業をスムーズに進めるために、事前に撤収計画を立てておきます。展示品や機材は丁寧に梱包し、次回の展示会でも使用できるように保管します。貴重品や壊れやすい機材は特に慎重に扱いましょう。
来場者へのフォローアップ(展示会 会期後)
展示会後のフォローアップは、展示会で得たリードを実際の商談に結びつけるための重要なプロセスです。迅速かつパーソナライズされたアプローチを行うことで、来場者との関係を強化し、次のビジネスチャンスをつかむことができます。
アンケート集計
展示会のアンケートは、来場者の興味や反応を直接知る手段です。アンケートから商談の有望度や興味のある製品やサービスを分析し商談のアポイントメントをとることでリードの獲得につなげましょう。
お礼メールの送付
展示会後すぐにお礼メールを送ることは、来場者との関係を強化するための大切なステップです。迅速なフォローアップが、商談の機会をつかむカギになります。
展示した製品やサービスのポイントを簡単におさらいし、再度関心を引くようにしましょう。同時に製品やサービスを直接紹介する機会をいただけるか依頼してみましょう。
DM(ダイレクトメール)の活用
展示会後に送るDMは、個別にパーソナライズされた提案を行うためのツールとして非常に有効です。お礼メールを送った後の次のステップとして、DMを通じて具体的な商談に繋げることができます。
まとめ
展示会出展は多くの準備が必要で、細かい作業が次々と襲ってきます。出展企業様が目指す目標を達成するためには、展示ブースの設営から運営、そしてその後のフォローアップまで、すべてが計画通りに進むことが求められます。ですが、これらすべてを自社だけで完璧に進めるのは非常に大変な作業です。
そんな時、信頼できる協力会社のサポートがあれば、スムーズに進行し、展示会を最大限に活用できます。 弊社では展示会に出展する企業様のために、最適なブース設計と運営をサポートさせていただきます。
サクラアルカスのサービス紹介資料ダウンロード【無料】はこちら
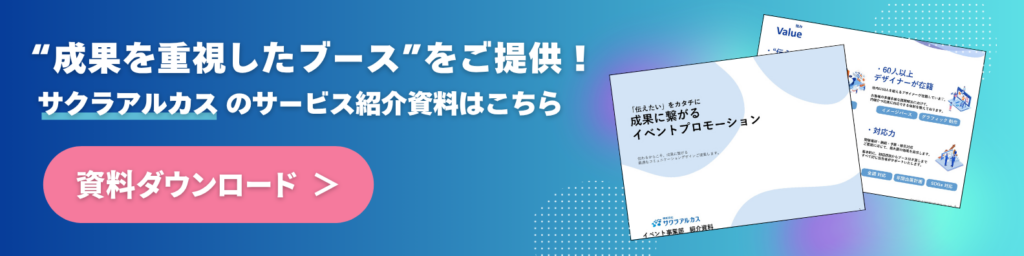
投稿者プロフィール
最新の投稿
 展示会パネル2026年2月6日展示会パネルデザイン完全ガイド|集客につながる制作・配置・コストの考え方
展示会パネル2026年2月6日展示会パネルデザイン完全ガイド|集客につながる制作・配置・コストの考え方 展示会準備2025年9月29日展示会ブースの集客を最大化!成果を生むレイアウト設計
展示会準備2025年9月29日展示会ブースの集客を最大化!成果を生むレイアウト設計 展示会準備2025年9月25日展示会出展ガイド:目的とターゲット合った展示会の選び方、5つのポイント!
展示会準備2025年9月25日展示会出展ガイド:目的とターゲット合った展示会の選び方、5つのポイント! オンライン展示会2025年9月19日オンライン展示会とは?リード獲得に繋がるメリット、費用、成功のポイントを徹底解説!
オンライン展示会2025年9月19日オンライン展示会とは?リード獲得に繋がるメリット、費用、成功のポイントを徹底解説!